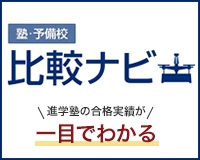- ハローワーク情報トップ
- >失業保険とは?
失業保険とは?
失業保険とは?
雇用保険の失業等給付には4種類あり、「求職者給付」、「就業促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用促進給付」があります。一般に失業保険と呼ばれるのは、求職者給付の中の「基本手当」のことを指します。
基本手当とは、雇用保険の被保険者(要するにサラリーマン)だった方が、退職し、働く意思と能力がありながら再就職できない場合に、失業中(就職活動中)の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するために支給されるものです。
一般には「会社を辞めたときに、もらえる手当」というイメージがあります。しかし、会社を辞めた人の全てがもらえるわけではなく、受給するためには様々な条件があります。
失業保険の受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすとき、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
失業保険受給までの流れ
1.離職票をもらう
離職後、勤務していた会社から「雇用保険被保険者離職票1・2」を受け取ります。いわゆる離職票です。
2.受給資格の決定
住居を管轄するハローワークに行って「求職の申込み」を行った後、「離職票」を提出します。このとき、以下の書類が必要ですので持参しましょう。
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
・住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
・印鑑(認印で可)
・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行ないます。このときに離職理由についても判定します。(簡単な聞き取りをされます。)受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。
3.雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されますので、必ず出席しましょう。「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参しましょう。受給説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明が行われます。ここで「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。
4.失業の認定
原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。
失業とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言うため、何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。職を探しているという実態が求められます。
5.受給
失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「4.失業の認定」、「5.受給」を繰り返しながら仕事を探すことになります。給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって異なります。
基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。
また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
1. 正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
2. 自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。
給付金額・給付日数一覧表
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金 額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。なお、基本手当日額には上限額が定められています。
(1)上限額(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
(2)給付日数
基本手当の給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は90日から360日で、年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などにより決定します。 倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なくして離職を余儀なくされた場合は特定受給資格者に該当し、一般の離職者に比べ手厚い給付日数となることがあります。
一般受給資格者(自己都合により離職した方および定年退職者の方)
15歳以上65歳未満
→被保険者期間(6月以上1年未満) 90日
→被保険者期間(1年以上5年未満) 90日
→被保険者期間(5年以上10年未満) 90日
→被保険者期間(10年以上20年未満) 120日
→被保険者期間(20年以上) 150日
特定受給資格者(会社都合、人員整理等で離職を余儀なくされた方)
30歳未満
→被保険者期間(6月以上1年未満) 90日
→被保険者期間(1年以上5年未満) 90日
→被保険者期間(5年以上10年未満) 120日
→被保険者期間(10年以上20年未満) 180日
30歳以上35歳未満
→被保険者期間(6月以上1年未満) 90日
→被保険者期間(1年以上5年未満) 90日
→被保険者期間(5年以上10年未満) 180日
→被保険者期間(10年以上20年未満) 210日
→被保険者期間(20年以上) 240日
35歳以上45歳未満
→被保険者期間(6月以上1年未満) 90日
→被保険者期間(1年以上5年未満) 90日
→被保険者期間(5年以上10年未満) 180日
→被保険者期間(10年以上20年未満) 240日
→被保険者期間(20年以上) 270日
45歳以上60歳未満
→被保険者期間(6月以上1年未満) 90日
→被保険者期間(1年以上5年未満) 180日
→被保険者期間(5年以上10年未満) 240日
→被保険者期間(10年以上20年未満) 270日
→被保険者期間(20年以上) 330日
60歳以上65歳未満
→被保険者期間(6月以上1年未満) 90日
→被保険者期間(1年以上5年未満) 150日
→被保険者期間(5年以上10年未満) 180日
→被保険者期間(10年以上20年未満) 210日
→被保険者期間(20年以上) 240日
就職困難者(障害者及び社会的事情で就職が著しく阻害されている方)
45歳未満
→被保険者期間(6月以上1年未満) 150日
→被保険者期間(1年以上5年未満) 300日
→被保険者期間(5年以上10年未満) 300日
→被保険者期間(10年以上20年未満) 300日
→被保険者期間(20年以上) 300日
45歳以上65歳未満
→被保険者期間(6月以上1年未満) 150日
→被保険者期間(1年以上5年未満) 360日
→被保険者期間(5年以上10年未満) 360日
→被保険者期間(10年以上20年未満) 360日
→被保険者期間(20年以上) 360日
失業保険が受給できる期間(受給期間)は、原則として「離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)」です。離職して離職票を受け取ったら、できるだけ早めに職安(ハローワーク)に行きましょう。
JDハローワークの特徴
- 全国の公共求職機関を
纏めた求職支援サイト - 職安(職業安定所)をはじめとした公共求職機関に関して、所在地等の情報をご確認頂けます。